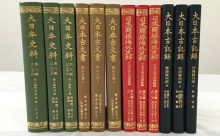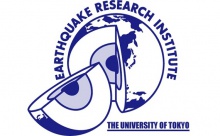本郷キャンパス
本郷
アジア研究図書館
アジア研究図書館は、総合図書館本館4階に開架フロアが開設されています。
学内に分散していた多数のアジア関係研究資料を集約し、アジア諸地域に関する研究を支援するための専門的な図書館です。
大学院法学政治学研究科附属近代日本法政史料センター(明治新聞雑誌文庫)
昭和2(1927)年に東京帝国大学法学部附属施設として開設された「新聞保存」を掲げた本邦初の施設です。明治期から昭和戦前期にかけての新聞・雑誌、錦絵等関係資料を所蔵・公開しており、国内外における多方面の研究活動、歴史編纂事業、展示等に役立てられています。明治・大正期に国内で刊行された新聞・雑誌コレクションとしては世界最大級とされ、コレクションは今も増え続けています。
工学・情報理工学図書館
工学・情報理工学図書館は専門分野が異なる10の図書室から構成されています。各分野最新の資料のみならず、明治初期の卒業論文や御雇い外国人教師の旧蔵書、江戸時代の絵図など貴重な資料も幅広く所蔵しており、工学・情報理工学関係史資料の保存・展示にも力を入れています。
大学院人文社会系研究科・文学部図書室
大学院人文社会系研究科・文学部図書室には、110万冊を超える蔵書があり、文学部3号館図書室、法文2号館図書室、漢籍コーナー、および各研究室に分散して配置されています。
経済学図書館
経済学図書館は、国内有数の経済学分野の専門図書館として、大正8(1919)年の発足以来、本学におけるこの分野の学習、研究活動を支える基盤的な役割を担っています。当館の資料は、関東大震災の火災による消失、思想統制による蒐書の困難、空襲対策の疎開など、多くの困難を乗り越えて受け継がれ、日々収集される最新の学術文献とともに、保存・提供されています。また当館では、企業・団体関連の資料の収集にも注力しています。
経済学部資料室
東京大学経済学部資料室の淵源は法科大学に開設された商業資料文庫にまで溯ります。以後、約1世紀の間に幾多の変遷を経て、現在では経済学研究科学術交流棟(小島ホール)3階に設置されています。
大学院教育学研究科・教育学部図書室
教育学研究科・教育学部図書室は、文学部教育学科時代の資料を引き継ぎ1950年4月に開設しました。教育学を中心に哲学・心理学・社会学・身体諸科学・図書館情報学等の資料を所蔵しています。資料は教育学部棟4階と医学部1号館地階に分散配置しています。
薬学図書館
薬学図書館では、薬学・有機化学・生化学分野の資料を中心に収集しています。蔵書のほとんどは雑誌ですが、単行書や薬学系研究科博士論文等も所蔵しています。開かれた専門図書館として、学内外の多くの学生・研究者に利用されています。
大学院情報学環・学際情報学府図書室
情報学環・学際情報学府図書室は、文学部新聞研究室、新聞研究所時代の言論統制やジャーナリズム研究に関する豊富な蔵書、社会情報研究所以来のマスメディア研究やマスコミュニケーション研究の資料を引き継いでいます。情報学環と社会情報研究所の組織統合以降は、文系・理系を問わず、情報に関わる社会現象や文化現象全般に収書範囲を拡大し、その主題分野は隣接諸領域にまで広く及んでいます。
大学院情報学環附属社会情報研究資料センター
情報学環附属「社会情報研究資料センター」は新聞資料を中心に、各種メディア情報資料を研究のために収集、整理し、それらの資料を学内外の研究者に利用していただくことを目的としています。
東洋文化研究所図書室
東洋文化研究所図書室の所蔵資料は、アジア諸地域のさまざまな分野にわたり、言語も日本語や欧米諸国語はもちろん、中国語・朝鮮語・アラビア語・ペルシャ語・タイ語・トルコ語など多様であることが特徴です。また貴重な漢籍を多く所蔵しております。
史料編纂所図書室
史料編纂所図書室では、100年以上にわたって影写・模写・写真撮影などの方法で作成・蒐集されてきた膨大な数の複製史料や、貴重な原本史料を、一般の図書・雑誌とともに所蔵・管理しており、歴史を研究する多くの方に利用していただいています。閲覧室に設置されたコンピュータ端末では、所蔵史料等のデジタル画像を閲覧することができます。
弥生
地震研究所図書室
地震研究所図書室は、地震・火山等に関する研究のための専門図書室(共同利用・共同研究拠点)です。約6万冊の図書、約2千5百タイトルの雑誌、地図類、貴重資料(災害写真・鯰絵などの和古書類)を所蔵しています。