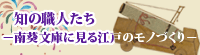■(2)旧蔵者と人脈からたどる この節では、資料の旧蔵者や著者、関連する人物を取り上げ、その「人脈」を軸にした展示資料の概観をする。(前節と同様、[ ]内の数字は資料番号を指示する。番号に下線を引いたものについては、該当する資料が、紹介されている人物・機関の旧蔵資料であったことを示している。なおこの節では、全資料の網羅的紹介はしていない。) 紀州徳川家出身の8代将軍徳川吉宗。彼のとった施策にはいくつかの科学技術に関する事柄が認められる。 第一に、元禄期に調進された国絵図のデータを補正して日本総図を作成させている。その責任者に抜擢されたのは、関孝和[→34]の弟子である建部賢弘[→35]・[→36]であった。建部はこの他にも、吉宗の意向に従い、中国から輸入された暦算書である梅文鼎(1633〜1721)著『暦算全書』(1723年)に訓点を施して献上している。
その協力者として建部が推挙したのは、京都の銀座役人・中根元圭(1662〜1733)である。(中根彦順[→38](1701〜1761)の父。)中根はその後、伊豆に出張して天文観測にあたっている。
なお、建部の和算の弟子の系列から、経世家として著名な本多利明[→19](1743〜1821)と弟子の最上徳内[→19]・[→20](1755〜1836)が出ている。 吉宗の関心は、さらに暦法の改革にまで及んでいた。晩年、長崎より西川正休(1693〜1756)を呼び寄せて天文方に抜擢し、西洋天文学に基づく新暦を準備させる。
その折にこの事業を補佐したのが山路主住(1704〜1773)である。(山路之徽[→12]・[→39](1729〜1778)の父。)この山路主住は関流の和算を集大成し、免許制度を整備したことでも知られている。しかし、吉宗のイニシアティブで進められた改暦事業も、吉宗の死去と、京都の土御門家の反発を招いて失敗に終わる。(この時に策定された宝暦暦[→04]には西洋の天文学の成果は採り入れられなかった。)
その後、幕府天文方はこの失敗の汚名を雪ぐかのように西洋の天文学の導入に邁進する。高橋至時(1764〜1804)・高橋景保[→17]・[→20]・[→38]親子によるラランデ(Lalande, 1732〜1807)の教科書の蘭訳本を翻訳する作業はその典型的な業績である。(この翻訳作業は、景保の弟で渋川家[→31]を継いだ景佑(1787〜1856)の代で完結する。)しかし、天文方と書物奉行を兼任した高橋景保はシーボルト事件[→11]の首謀者として入牢し、獄死する。
寛政の改革を主導した松平定信(1759〜1829)は周知の通り、吉宗の孫で田安家[→44]・[→45]・[→49]の出身である。この寛政期の改暦によって寛政暦[→03]が策定された。和学講談所が開設され、『群書類従』[→23〜26]の編纂が開始されたのも寛政期のことである。(1793年)
次いで、天保期には水野忠邦[→30](1794〜1851)による天保の改革があり、この時にも改暦が行われて天保暦[→03]・[→05]が策定された。この西洋天文学の成果を導入した暦法をもって、幕府の改暦事業は終わる。
この間、天文方の外でも平田篤胤[→09]が暦に関する著述を著し、幕府から糾問を受けている。(平田の門弟に紀州藩士・石井寛道[→07]がいる。)
なお、水野忠邦に招聘された国学者村田春門[→29](1765〜1836)は、平田と反目していたとのことで、水野に対して平田を譴責する文書を呈している。 さて、再び吉宗の施策に戻って、本草学・物産学に関する事柄を見てみよう。
吉宗が最も力を入れ、成功した事業として筆頭に挙げられるのは朝鮮人参[→50]の国産化であろう。対馬の宗家を巻き込み、朝鮮の国禁を犯してまでその種を入手させることから始まったこの事業は、その栽培が軌道に乗るまで数年間の年月を費やす。その間、田村藍水[→51](1718〜1776)をはじめとする本草学者が動員され、研究にあたっている。
一方、国産化が検討されたのは人参だけではなかった。他の有用で利用可能な薬材を国内において発掘する作業も積極的に進められた。採薬使を派遣することでその事業は進められたが、この役を命ぜられた一人にやはり本草学者である阿部将翁[→43](1650〜1753)がいた。また松岡玄達[→42](1668〜1746も一時、江戸に呼ばれている。(田村藍水は阿部将翁の弟子であったとも言われている。)
松岡の門下からは、『本草綱目啓蒙』の編者として著名な小野蘭山[→41](1729〜1810)が出る。([41]の旧蔵者は狩谷棭斎(1775〜1835)、次いで森立之(1807〜1885)へ。)小野もまた、文化年間に幕府の招請を受けて江戸に出て採薬事業を務めている。小野の元からは有能な本草学者が輩出している。京都の山本亡羊(1778〜1859)、尾張の水谷豊文(1779〜1833)、紀州の小原桃洞[→47・48]の三人をここでは挙げておこう。さらに、山本の弟子に伊勢の西村広休(1816〜1889)がおり、水谷の弟子には日本最初の理学博士となった伊藤圭介(1803〜1901)がいる。(伊藤はシーボルトにも学んでいる。)
この本草学の系列の末尾に位置するのが、明治期に「博覧会男爵」の異名をとった田中芳男[→50]・[→51]・[→69]・[→70]・[→71](1838〜1916)である。(田中の元には西村広休の旧蔵書が一部伝わっている。)田中の旧蔵書はその多くが、昭和7年に東京大学総合図書館に寄贈されている。今回の展示でも田中旧蔵書を数点紹介しているが、南葵文庫とは直接的な関係はないものの、上記の学系図を勘案して採用している。
なお、吉宗の指示によって他の分野で得られた成果として、染色[→67]と皮革[→68]が挙げられる。
 最後に見ておきたいのは、吉宗の実家である紀州徳川家から南葵文庫へと至る人脈である。紀州徳川家には常時数名ずつ儒者が登用されていたが、享保期に登用されていた儒者の一人に榊原霞州[→06]・[→34]・[→35]・[→36]がいた。彼は建部賢弘等の和算書を筆写して紀州徳川家に納めている。もう一人、ここで紹介をする儒者は、天保期の人物、遠藤勝助[→52]・[→53](1789〜1851)である。彼は高野長英[→52](1804〜1850)・渡辺崋山[→52](1793〜1841)等と交わっている。(渡辺崋山は田原藩に大蔵永常[69]を招いて殖産事業にあたらせたが、成果が上がらないことで決裂している。)高野の門弟に、内田五観[→08]・[→52](1805〜1882)・奥村増貤[→40](生没年未詳)がいる。(奥村は平田篤胤との交流もあった。[52]の旧蔵者は、小原桃洞の孫、小原良直[→47・48](1797〜1854)。)
遠藤と同時代に紀州藩の付家老の職にあった水野忠央[→27]・[→28]・[→29]・[→53](1814〜1865)の存在は、彼の編纂した『丹鶴叢書』[→27]・[→28]・[→29]、そして藩校として開設した紀伊国学所[→28]、蘭学所によって、紀州藩の政治・学術を考える上で逸することのできないものである。 明治を迎え、南葵文庫が整備される際に、数多くの寄贈書・購入書がもたらされた。紀州藩士の国学者で、後に『古事類苑』などの編纂事業に携わったことで知られる小中村清矩[→23〜26](1821〜1895)の旧蔵書も、数多く南葵文庫に納められている。彼の旧蔵書には歴史上の著名人のものが多数含まれている。この特別展で紹介をした『群書類従』の旧蔵者を例として挙げれば、戯作者滝沢馬琴[→23](1767〜1848)、大黒屋光太夫(1751〜1828)の息子で漢学者の大黒梅陰[→23](1797〜1851)、幕臣・狂歌作者の大田南畝[→24](1749〜1823)、国学者の前田夏蔭[→25](1793〜1864)、幕府書物奉行を務めた近藤正斎[→26](1771〜1829)等がいる。(この近藤正斎は四度にわたる北方探検に従事し、択捉島[→20]にも渡っている。) 南葵文庫に多数の旧蔵書が納められている人物は他にも、坂田諸遠(1810〜1897)、島田重礼[→37](1838〜1898)、海保漁村[→22](1798〜1866)などがいる。 南葵文庫が最終的にはどのような蔵書の構成を持っていたのかについては、今後の調査を待たねばならないが、上記のように個別資料の旧蔵者を追跡するだけでも、学術的新知見が得られる期待は十分にある。 |