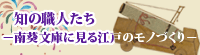著者の大蔵永常は、明和5(1768)年に豊後国日田郡の農家に生まれた。永常は各地に赴き、農学者として多くの著作を残した。代表的なものに、『農家益』『農具便利論』『除蝗録』『綿圃要務』『製油録』『広益国産考』『甘蔗大成』などがあり、生前に約30部、70冊の書物を公刊した。
天保4(1833)年には駿河国田中藩で製糖、櫨の栽培などの産業開発を行い、翌5年には三河国田原藩の江戸家老、渡辺華山の推薦によって同藩の興産方に任命された。しかし天保10(1839)年の蛮社の獄によって渡辺華山が国許蟄居を命ぜられると、すぐに永常も田原藩から追放された。その後天保13(1842)年に浜松藩の興産方に採用されたが、生涯の多くをフリーランサーとして生きた。1860年死没説もあるが、明確ではない。
本書には、幕臣であり儒者でもある羽倉簡堂が文政11年(1828)7月に序文を寄せている。本書の刊行は、文政11年を初めとして、同12年、同13年、天保11年、弘化3年と多くの版を重ねている。本館所蔵本は、文政13年版である。
本書は、葛粉と遠州掛川で実見した葛布の作り方を詳述している技術書である。葛の蔓はその繊維から葛布を、葉は牛馬のえさに、根は乾燥させて薬用になり、また葛粉もとることができるので、少しも無用なところがないと説いている。
葛根の利用は、『出雲風土記』や、奈良県橿原市の藤原京から出土した木簡によって、8世紀初頭まで遡ることができる。一方、葛粉がいつ頃から製作されるようになったかは、『延喜式』に「黒葛」の名称がみられ、これを葛粉とする説もあるがはっきりしていない。
本書にも言及されている葛粉の産地として名高い吉野葛の名称は、永享2(1430)年『鈴鹿家記』にみられる。
(荒尾美代)
■大蔵永常の他の著作で、下記のものが総合図書館に所蔵されている。(抜粋)
[B40:1093]田家茶話/[B40:584]勧善夜話後編/[B40:598]奇説著聞集/[B40:920]民家育草/[D30:36]文章仮字用格/[D30:395]文章かなつかひ/[XB10:167]国産考/[XA10:20]除蝗録/[XA10:252]農家益初篇/[XA10:253]農家益後篇/[XA10:254]農家益続篇/[XA10:266]農家心得草/[XA10:269]綿圃要務/[XA10:282]豊稼録/[XA10:300]農稼業事後編/[XA10:314]耕作便覧/[XA10:399]農稼肥培論/[XA10:904](勧農叢書)老農茶話/[XA35:4]農具便利論/[XB30:58]製油録/[XB30:61]油菜録/[YA:109]徳用食鑑