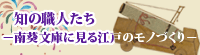ここに展示する三島暦も、伊勢暦
[→03]と同じ天保15年の暦で巻頭に説明文が書かれている。
この暦は巻子であるが、三島暦は一般には綴じ暦で、巻子は少ない。この巻子の最初の部分には金泥が施されている。「御暦師 河合龍節藤原隆定」とあるが、三島暦はこの河合家が代々頒行してきた。地方暦の中でももっとも古い暦の一つで、現存最古の三島暦としては、断簡であるが、永享9年(1437)の暦が残されている。「三島」とは書かれていないが、栃木県真岡市の荘厳寺で発見された康永4年(1345)の仮名版暦は三島暦の可能性が高く、年初から年末まで残されている仮名版暦としては、もっとも古い。康永4年の暦も永享9年の暦も宣明暦法(貞観4年(862)〜貞享元年(1684)施行)である。この宣明暦法は唐からもたらされた暦で、渋川春海(幕府初代天文方、1639〜1715)によって、日本の暦法が編纂されるまで、800年以上使われていた。この時代、地方暦によっては暦日(1年の日数)の違うことすらあった。
この暦の冒頭には「天保十五年きのえたつ乃天保壬寅元暦 ・・・ 凡三百五十五日」とあるが、天保壬寅元暦法によって計算されたこの年の1年が355日であることを示す。次の行からこの年に対する暦注が書かれ、その後が、毎月の暦になっている。上段から日付、その日の干支、暦注の「十二直」、五行、中段に、「ひがん」などが書かれ、下段は暦注がいくつもかかれる。この形が、一般的な暦の内容であり、他に、日月食がある場合には1行の中にその現象が書かれる。
この三島暦は南葵文庫へ石黒忠悳(1845〜1941)が寄贈したもので、箱書きに、明治42年10月の日付がある。また、書簡がつけられていて、三島本家河合龍節から、世古直道宛と、世古から、石黒家に宛てた手紙がつけられている。河合からの書簡で、この暦が献上暦の雛形として、河合家に残されていた暦であったらしいことがわかる。石黒忠悳は医者、佐久間象山(1811〜1864)から影響を受ける。維新後、軍医総監、子爵。
(伊藤節子)