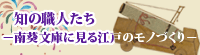■(1)分野による区分
本企画展では全72点の図書、資料を紹介するが、展示の配列は、全体を大まかな分野に分けて6つのグループとしている。以下、その概観を述べることとする。(文中の[ ]内の数字は、展示資料の番号である。)
[1] 天を知る (展示資料番号[02]〜[11]) >>個別資料解説
いかなる「モノづくり」においても、その基礎には何らかの世界観が横たわり、世界そのものに対する知識や経験が生かされている。それではどのような宇宙観、世界観を近世の人々は持っていたのか。この最初の区分においては天文・暦学関係資料を紹介したい。 東アジアの伝統科学の中で、最も精密に数量化された分野は暦学といっても間違いなかろう。(単に「天文学」と言ってしまうと、近代以前の文脈では占星術的要素も含まれてしまう。)そもそも暦を作成し民に正確な季節と天文現象を伝えるのは為政者の務めであった。古代以来この考え方は東アジアのほぼ全域において一貫して保持されていた。その実現のために、中国などでは分秒単位の天文観測が国家的規模でなされ、毎年の暦が策定されたのである。当代随一の暦学者・数学者がその作業には動員されていた。古代中国のこのような伝統を近世日本の江戸幕府も、意識的かどうかは別として踏襲することになる。1685年に幕府は貞享暦という暦法を策定し、本格的な改暦事業に着手する。以後、吉宗の享保の改革に始まる近世の三大改革では、必ず改暦事業が話題にのぼり、実現している。吉宗が宝暦の改暦に着手した後、寛政暦、天保暦と幕府の改暦事業は進展する。 暦[→03]・暦[→04]・三島暦[→05]は近世期に伊勢や江戸、三島などの各地で作製された暦である。書冊としての暦の形式は折り本、綴じ本など、地域の版元によって様々であるが、内容は一括して幕府天文方が作成の権限を持ち、朝廷の認可を形式的に受けて発行されていた。暦を作るための天文観測やデータ処理のための計算には、常に最先端の学術が投入されていた。近世前半期、西洋天文学が導入される以前の天文・暦学の規範となったものは中国の元代に作られた『授時暦』(元・明王朝において、1281〜1644年施行)である。近世の多くの暦学者はこの暦法の研究に努力を傾けている。その一端は授時暦立成[→06]に現れている。 一方、精密科学とは必ずしも言えない天文学の利用のされ方もあった。軍気用法[→02]に見られる星の見方は、占星術に近い。精密な天文現象の追究と表裏一体を為すかのように近世日本には吉凶を判じるための古代的な「天文学」も残存していたのである。 近世後半になると、盛んに西洋の天文学の知識が日本にもたらされる。(周髀算経正解図[→07]・新制天地二球用法記[→08]・華術三才噺[→10])西洋的な太陽系モデルを日本人が知るのもこの頃からである。[08]は阿蘭陀通詞、本木良永(1735〜1794)が蘭書から翻訳をした当時の西洋天文学の概説で、初めてコペルニクス説を紹介している。一方、[07]は国学者でありながら中国系の天文学を信奉する著者石井寛道(1763〜1843)が、西洋系の天文学と仏教的宇宙論(須弥山説)を論難した書である。このように近世後半はいくつかの宇宙論が知識人の間に浸透し、せめぎ合う時代となっていた。西洋系天文学の知識が波及した異色の分野としては、[10]の生け花(未生流)があろう。そこには太陽中心の太陽系モデルが描かれてある。庶民に至るまで、このような知識は(興味本位という位相もあろうが)浸透していたのである。 さて、西洋天文学の受容に邁進した幕府天文方も、常に政治的に平穏無事であったわけではない。六彣違測集[→11]は高橋景保(1785〜1829)他、シーボルト事件(1828年)に連座した人々の判決申し渡しである。シーボルト事件によって一時期、蘭学に対する風当たりは強まった。国学者平田篤胤(1776〜1843)も、暦学に関する著作を残している。天朝無窮暦附録[→09]は、自著『天朝無窮暦』(1834年)に向けられた天文方からの意見についての弁明書である。
[2] 地を知る (展示資料番号[12]〜[22]) >>個別資料解説
天文学と同様に、地理学、世界情勢も近世日本人にとっては興味関心の対象としてあった。海禁政策、いわゆる「鎖国」のもとにあっても海外に対する好奇心、知的探究心が皆無となることはなかった。むしろ、限られた情報源だけであったためにその探究心はより先鋭化されたと言うべきであろうか。 町見術[→12]は、近世前半期の測量術(町見術)の秘伝書である。伊能忠敬ばかりが日本の地図作りでは著名であるが、彼が活躍をするほぼ一世紀前から日本人の間で町見術についての知識は体系化されていた。伊能の地図作りも基本的な技術はその町見術に多くを負っていたのである。当時の町見術を用いて作製されたであろう地図の一例が対馬国図[→13]である。 西欧伝来の地図、地理学書からの翻訳も近世後半には盛んになる。(紅毛天地二図贅説[→14]・喎蘭新訳地球全図[→15])天文学の知識の普及と軌を一にして、大地が球形をしているという「地球」の概念は日常的なものとなっていく。さらに世界地理の紹介は、地球上には様々な国・地域があることを日本人に知らせることとなった。折しも18〜19世紀になると異国船が日本近海に現れ、にわかに海防問題が意識されることになるが、基本的な情報として異国船の国籍を識別するための旗章をまとめたのが各国旗図[→16]である。世界情勢を直接的に肌で感じる時代が再び日本に訪れたのである。洋学雑記[→22]はヨーロッパ情勢も簡単に触れた宇田川榕庵(1798〜1846)による蘭学の雑記帳である。 世界地理のみならず、日本地理全般についても知識の刷新、見直しが近世後半には顕著となった。地勢提要[→17]は高橋景保が伊能忠敬の実測に基づいて日本各地の経緯度などの情報を簡単に参照できるようにまとめたもの。蝦夷チャランケ并浄瑠璃言 唐太事状 蝦夷暦[→18]・蝦夷風俗人情之沙汰[→19]・蝦夷風俗人情之沙汰附図[→20]・北夷考証[→21]は、近世日本においてこれほど近くにありながら長らく意識の外にあった北方地域(蝦夷地、唐太、千島)に関する資料である。18世紀以降、ロシアの南下に伴う蝦夷地周辺の緊張が幕府を動かし、何度かの探検事業や出兵警備へと発展する。これらの資料はその先駆けを為す時期のもので、異国として見た蝦夷地の民俗・地理情報が盛り込まれている。
[3] 知を作る (展示資料番号[23]〜[33])>>個別資料解説
近世はまさに出版文化の時代であった。玉石混淆ではあるものの、おびただしい情報が生産され、流通する世界が出現した。古典から、ヨーロッパの最先端の知識まで、ありとあらゆるジャンルの成果が書籍として刊行された。(なお、刊行物だけが知識の流通を担っていたわけではなく、それらがさらに筆写されて流通するという二次的波及経路が近世日本の社会にはあった。) ここでは、出版そのものの過程を校正刷りという形で示している丹鶴叢書[→27]をはじめとして、刊行された印刷物がどのような読者を持っていたのかを蔵書印から紹介したい。(群書類従[→23〜26]・丹鶴叢書[→28]・[→29]・後水尾院年中行事[→30]・居行子[→31])書籍には著者がいるとともに、読者があって初めて、その内容が知識として社会に還元されていく。その当然の事柄をあらためて確認しておきたい。 書籍は文字情報ばかりではなく、図像による情報も伝達する。近世の出版物にはふんだんに図像が用いられているが、博物学の分野ではこのことが威力を発揮している。一角纂考[→32]・物類品隲[→33]は時代の雰囲気を示す博物趣味の書籍である。[32]は当時の日本人には未知であった「イッカク」をヨーロッパの書籍を参考にしつつ図入りで紹介している。[33]は平賀源内(1728〜1780)が発案した物産会の記録である。彼の企て以後、各地で同様の会が催されることとなる。
[4] 理を作る (展示資料番号[34]〜[40]) >>個別資料解説
読み・書き・そろばんというフレーズで代表されることが多い初等的な教育内容の中でも、この「そろばん」に代表される数的処理能力は近世の日本において和算として結実し、その学術的成果は多彩であった。「天地の理を知る」という句があるが、和算家たちの活動は自らの探究によってその「理」(ことわり)そのものを創出していったと言うにふさわしいものがある。 ここでは、総合図書館の中でも数ある和算書の内、南葵文庫あるいは本特別展の趣旨に関わるものを数点紹介したい。(総合図書館には明治時代以来収蔵され、奇跡的に関東大震災での火災を免れた和算書が総計1300タイトルほど残されている。) 関氏雑著[→34]は、和算家として最も著名な関孝和(?〜1708)の著作をまとめたもので、雑技[→35]・建部先生綴術真本[→36]は関の弟子である建部賢弘(1664〜1739)に関わるものである。関孝和は知名度が高い割には、確実な伝記資料はほとんど残されていない。ましてや、その自筆草稿などは今のところ全く確認されていない。南葵文庫に伝来するこれらの資料は、関孝和没後の早い時期、そして建部賢弘が存命中に筆写されたという点で非常に貴重なものである。(筆写した人物は、紀州藩儒・榊原霞州(1691〜1748)ということが判明している。) 小学九数名義諺解[→37]は、関孝和の孫弟子にあたる沼田敬忠(生没年不詳)という人物が著した書で、中国の古典に現れる算法の名称を実例入りで解説している。従来知られていなかった初期関流に関する実態を述べるとともに、儒者・三宅尚斎(1662〜1741)が測量術に秀でていたという事実を述べる異色の書である。 近世日本の数学は、戦国時代の末期に導入されたと思われる「そろばん」の算術からスタートしている。その解説書である吉田光由(1598〜1673)著『塵劫記』(初版1624年)が人気を博したことを皮切りに、続々と算法書が続いていく。(算術の問題を出してその解凍を競う風潮も『塵劫記』が口火を切っている。)その背景には、算術が商人の技としてばかりでなく、土木や徴税などの治世全般に必要な実学の一端を担うものとして意識されるようになったこともある。それとともに、学術的な研究も相まって進み、関孝和の出現となるのである。 関孝和以後、和算家と呼ばれる人々は全国各地に数百人という単位で輩出する。彼らが学んだ数学には遊びの要素もあり、かたや実践を主とした研究もあった。勘者御伽雙紙[→38]は「遊び」の要素を強調する数学をまとめた一編。数学パズルの近世版といってもよいであろう。一方、比例尺解義[→39]・算学必究[→40]は実学を志向する意図で編まれた算書である。[39]はヨーロッパから伝来した「比例尺」(ガリレイ・コンパス)の解説書で、西洋数字やアルファベットが記されており、吉宗以降の西洋知識解禁の影響をここにも見ることができる。(この「比例尺」そのものはこの紹介があっても、ほとんど普及はしなかった。そろばんの方が格段に便利だったためであろう。)[40]もまた、数学の有用性を訴える内容で、これも西洋の計算道具である「籌算」(ネイピア・ボーン)を紹介している。
[5] ものを知る(展示資料番号[41]〜[53]) >>個別資料解説
世界のあらゆるものを探索し、分類する博物学。近世日本においては、中国の伝統的な薬物学である本草学を母体とし、多方面へ深化を遂げていく。従来の薬物学はもとより、薬用だけではない実用性を自然物の中から見いだす「物産学」が近世後半期には生まれる。そして自然物を好奇のまなざしで探究する精神、あるいは分類しようとする精神、写実性を求める描写法の展開、等々、ありとあらゆるこの「学」にまつわる志向性が開花し発露したのが近世本草学の姿であったと言えよう。学でもあり、趣味とも言えるこの本草学は、庶民から大名まで巻き込んで展開をした。そこには多種多様な知識が蓄積され、人脈が構築されていた。むしろ現段階では、そのような江戸時代の本草学・博物学そのものを歴史的に分類する基準が必要なのかもしれない。ここではそのような本草学の一端を紹介する。 爾雅紀聞[→41]は、中国の古典『詩経』から本草学に関するものを抽出し、日本語による解説を付している。漢字文化圏内での本草学用語の異同は、時に致命的な結果を招きかねないのである。怡顔斎蘭品[→42]・採薬使記[→43]は、吉宗の採薬使派遣事業に深く関わった人物の著作、あるいは聞き書きである。 和漢写真補遺[→44]は植物、啓蒙蟲譜図[→45]は「虫」の類(厳密には昆虫だけではない)、翻車考[→46]は魚類(マンボウ)を主題とした本草関係資料である。なお、山海異経[→49]は一見すると鳥類図譜のようであるが、掲げられているのはすべて古典籍に現れる想像上の「鳥」で、異色の資料。 桃洞遺筆[→47・48]は紀州藩の本草学者小原桃洞(1746〜1825)の遺録をまとめたもので、本草学全般にわたっている。 人参書[→50]・参製秘録[→51]は、徳川吉宗が積極的に進めた朝鮮人参の国産化に関連した資料として紹介する。[50]は人参の図譜、[51]は人参の収穫から加工法までをまとめた解説書である。 自然の猛威に対して人間の側の備えを講ずることもまた、本草学の守備する領域であった。「救荒本草学」というべきものであるが、ここではその一つとして二物考[→52]を紹介する。(参考資料として、定府官録帳[→53]を併置しているが、これは江戸詰紀州藩士の一覧である。)
[6] 作り 試し 伝える(展示資料番号[54]〜[72])>>個別資料解説
技術に関わる人間が自らの技術について語ること、これは簡単なことのように見えて、実際には非常に困難を伴う作業のはずである。如何様にも言語化できない情報が技術そのものを成り立たせている場合(勘やコツいったもの)も多々あろうし、秘伝と称して制度的に言語化を拒絶する場合もあるだろう。そのような障害が現代と同じようにあったであろうにもかかわらず、近世の日本人は職人の技に関する記録を残す努力を怠りはしなかった。何のためにその行為は為されたのか?それら知と技を求める人々が多数いたこと、今の筆者にはそのような答しか浮かんでこない。そのような人々の意識がメディア(出版)を盛り立てたであろうし、逆に、メディアが新しい知と技に対する需要を開拓したこともあるだろう。 職人の技といっても多種多様である。生活に関する技、美を追究する技、はたまた軍事に関する技もある。本草学や和算のような学問の成果を土台とした技もある。かたや遊びのための技もある。もちろん、この展示によってそれらのすべてを紹介することはできない。わずか数点ではあるがそれらの資料の背後に、限りない人間の労苦やよろこび、歴史的背景が横たわっているであろうことをぜひ想像していただきたい。 稲冨流砲術書[→54]・安盛流火薬書[→55]・心的妙化流[→56]・礟家技精鍛捷弾誌[→57]・天山派備忘録[→58]は、鉄砲と砲術に関する資料である。砲術の様式化、形式化が進む近世前半期の資料(→[54]〜[56])と、対外防備が問題となった近世後半期の資料(→[57]・[58])を併置する。一方、砲術に不可欠な火薬調合の技術は、江戸時代には平和的利用へ転用がなされ、「花火」として庶民の娯楽にまで広がっている。(花火競技[→59]) 自然物としての花卉を一つの構図の中に切り取り、配置する技によって魅せる華道の資料(立花百瓶図[→60])。儀礼の様式美を追究する意識は、組紐(結方図[→61])と折形(番外折形[→62])に象徴されている。 職人たちの名鑑、鑑定便覧などが、印刷物として刊行されたのも江戸時代の出版文化の産物である。(古今金工便覧[→63]・狩野氏画工道統並印譜[→64)かたや、近世以前の古い伝統を守り続ける技(造園術)の伝授書も残されている。(中院御流縄張之図式[→65])寛政期の人々の興味をそそった、新奇な建築技法が印刷された書籍もある。(御堂再建[→66]) 吉宗の政策が関わって出現した記録資料もある。染色法[→67]は、吉宗が御小納戸の浦上氏に命じて染色を実施させたときの記録で、古記録の染色に関する記事を再現させるなどしていた模様である。柔皮染法[→68]は、西国での古武器調査の際に大和国高市郡より発見された、皮革の染色に関する古文書の写しである。 製葛録[→69]は農学者大蔵永常(1768〜1860)の数多い著作の中の一冊で、「葛」という商品作物にまでその視点を向けていることに着目してここで紹介をした。 唐方渡俵物諸色大略絵図[→70]・ひとよ川[→71]・勇魚取絵詞[→72]は、水産業に関わる資料である。[70]は近世後半期の日本の対中国輸出品として知られている「俵物」の図譜。[71]は九州地方の魚釣りや漁法を紹介した図譜の写し。最後の[72]は近世期で最も大がかりな漁法である捕鯨の捕獲から加工過程、さらには鯨の解剖図や諸道具までを描いた絵詞である。
|