土 肥 慶 蔵 年 譜
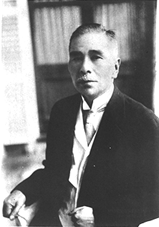
土肥 慶蔵(どひ・けいぞう) 慶応2年(1866)〜昭和6年(1931)
土肥慶蔵は、慶応2(1866)年、越前武生藩の藩医五世石渡宗伯の次男として、越前府中松原(現、福井県武生市)に生まれ、明治22(1889)年、24歳のときに、母方の叔父土肥淳朴の養子となり、土肥姓を名乗る。
明治13(1880)年、15歳のとき、兄秀實に伴われて上京し、下谷(現、台東区下谷)の進學舎でドイツ語を学び、同年、東京外国語学校(現、東京外国語大学)に入学。明治18(1885)年、東京大学医学部予科に入学、明治24(1891)年に帝国大学医科大学を卒業後、附属第一医院外科医局に入局。医局ではお雇い外国人教師として来日していた外科医スクリバの助手となる。
明治26(1893)年、文部省留学生として渡欧。はじめ外科学を修めたが、帝国大学医科大学皮膚病梅毒学の初代教授村田謙太郎が亡くなったために、文部省から、皮膚科学を学ぶようにと命ぜられ、ウィーン大学でカボシーに皮膚科学を、ランゲに黴毒学を学び、さらにパリ大学でギュイヨンに泌尿器科学を学び、明治31(1898)年1月に帰国した。
帰国直後の同年2月、東京帝国大学医科大学に新設された皮膚科梅毒学講座を担任、6月には主任教授となり、大正15(1926)年まで在籍した。その間、諸種の皮膚病を発見し、独特の皮膚治療法を考案し、特に理学的療法に先鞭をつけるなど、28年間にわたってわが国の皮膚科泌尿器科学の開拓・育成に努めた。また、日本皮膚科学会、日本性病予防協会(現、性の健康医学財団)を創立し、その会頭を務めたほか、多くの学会の指導にあった。
ウィーン大学在学中にカボシーからムラージュの製法を学んだ。ムラージュとは蝋製標本で、皮膚疾患の記録として人体の型とおりに作り、彩色をしたものである。帰国後、洋画の修行も積んでいた伊藤有(1864−1934)にムラージュ製作を依頼した。伊藤のムラージュは三千点にのぼり、現在東京大学総合研究博物館に保存されている。また300点あまりの模写図は「日本皮膚病黴毒図譜」(明治43年刊)に収められている。
その一方で、東京帝国大学医科大学時代の同級生呉秀三や医史学界の泰斗となった富士川游らの影響を受け、医史学にも興味を持つに至った。古典に通暁し、かつ漢文や外国語を駆使しての『世界黴毒史』(大正10年刊)は画期的な名著である。また、大学予備門時代に古道人に文章に関しての教えを受け、堂号を「鶚鷲堂」と命じられた。「鶚軒」はそれを転化したものであるといわれている。昭和6(1931)年、東京で亡くなった。享年65歳。
参考資料:
- 土肥慶蔵先生生誕百年記念会編「土肥慶蔵先生生誕百年記念会誌」 (東京 土肥慶蔵先生生誕百年記念会 昭和42年刊)
- 山口英世著「真菌(かび)万華鏡」(東京 南山堂 平成16年刊)